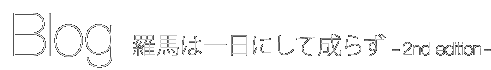「正倉院」展2016.11.11
今年の正倉院展はガラスの展示はほとんどありませんでした。
今回の注目展示品の1つはチケットにも掲載されている「漆胡瓶」。
この漆胡瓶をみると同じ正倉院蔵の「白瑠璃瓶」を思い浮かべます。

(日本経済新聞社1965『正倉院のガラス』より)
まるで滴が垂れ落ちるような形はガラスならではの表現で、道具でこねくり回すとむしろうまくこの形がだせません。吹き竿の先端の軟らかいガラスは、竿を下に向けると垂れていきますが、この垂れていく自然の力を利用した方が美しい滴形になりやすい。胴部の膨らんだあたりから別のガラスで把手をつくっていますが、この形も独特で面白い。把手の、注ぎ口の背面部分にぴょこっと飛び出した部分があり、把手を持ってこれを親指で押すと自然と首が傾き、中の液体が注ぎやすくなるという工夫がされています。漆胡瓶にはそのような工夫はなく、その代わり、把手は「?」マークのように一度上方へ大きくカーブを描く形になっています。口には蓋がついていて、この蓋は把手の根元で鎖とつながっていますが、液体を注ぐ時にいちいち蓋をとっていたのでしょうか?いずれにせよ、「注ぐ」という行為に対して意識した水瓶です。
注ぎ口は上から見ると口縁部が内側へ湾曲していて、液漏れ防止策が施されています。
『正倉院のガラス』には、”この種の瓶は「胡瓶」と呼ばれていたことが東大寺献物帳から分かっている。”胡”は主としてイラン民族を指すことから、「胡瓶」=ペルシア式瓶ということになる”、という旨の説明が書かれています。さらに、この瓶はアルカリ石灰ガラスで、おそらく製作に7~8人必要だった、ペルシアで作られ、中国経由で日本に渡ってきたとも書かれています。個人的には、何を根拠に製作人数を7~8人としたのかが気になります。レバノンでは形は違えど、把手付のガラスを一人で作っていました。
レバノンのガラス職人
由水常雄(2009)『正倉院ガラスは何を語るのか』は正倉院ガラスに特化した面白い本ですが、白瑠璃瓶をササン朝ペルシア時代の優れたガラス技術を継承した地で作られたとし、これと同じようなガラス瓶の頸部が出土しているイラク・サーマッラ地方が産地だとしています。