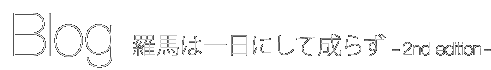新沢千塚 里帰り展2014.07.11
奈良県橿原市にある橿原市博物館にて126号墳出土品の里帰り展が開催されています。
ここは旧千塚資料館で、2011年にガラス玉つくりの体験をさせていただいたところ。
1階はガラス張りになっていて土器の復元やナンバリングの作業が見えるようになっていました。
2階が展示室となっていて、常設展室と企画展室に分かれています。
普段は別の場所で展示されている出土品を集めての展示、ということで「里帰り展」。
紺色ガラス皿とカットガラス碗が出土しているので、実物が見れると思っていたんですが、
こちらは残念ながら復元品(常設展)の展示でした・・・。
新沢千塚古墳群
博物館の裏手にはもう古墳群が広がっています。約600基もの古墳があり、古墳は4世紀末頃から作られ始めたとされています。
円墳、前方後円墳、方墳、長方形墳などバラエティに富むのが特徴。この中でも126号墳と呼ばれる古墳(5世紀後半)からは金銀
の装飾品、ガラス器などが発掘され、この時代の吹きガラスでしかも完形品は珍しく注目を浴びました。 とはいえ、写真を見ても分かるように、
見た目は何の変哲もない小山・・・
カットガラス碗
実物を持たせていただきました・・・・*
というのはウソです。過去に試作されたものに触れることができます。
復元品とはいえ、本当にうまいことできていまして、口縁部のガタガタ感も実物そっくりです。
実物は透明なガラスで作られた口径7.8cm、最大幅8.7cm、高さ6.7cm、の小さな碗。
復元品のように丸く削られて斑点のように見える模様が胴部中央あたりから下方へ3段(各19個のカット)、
少し間を空けて1段(同9個)、また少し間を空けて1段(同4個)。ポンテ痕はない。
これらの斑文は削られているがために、ガラスが磨りガラス状になって曇ってみえるので目立ちますが、
実は最初の3段の間には光沢がでるほど磨かれた円文が配置されています(2段、各19個)。
こうして中途半端に研磨された円文と完全に磨かれた円文が交互に、合計5段配されています。
下方の2段の間には完全に磨かれた円文は見られません。報告書では未完成品なのか完成品なのか
結論は下していません。
吹きガラスとして見ると技術的には難しいものではないですが、上部で一度、径がすぼまり、再び上部へ向けて
広がり始めたところで吹き竿から切り離されているというところが不可解なところ。吹き竿からうまく切り落とそうとすれば
径がすぼまったところがベストなんですが(チューペットが良い例。真ん中のくびれているところできれいに
折って二つに分けることができるでしょ?)、切り離すには難しい部分で切り離しています。
吹き竿から切り離した後に口縁部を外側に広げた可能性も無くはないですが、このガラスにはポンテ痕がないので、
ポンテを使わない方法を考える必要がある。しかし、口縁部を外側に広げるには口縁部を一度加熱して軟化させる
必要があるのですが、実物の口縁部切り口が鋭く、再加熱されたようには見えないので吹き竿から切り離した後に
広げた可能性は低いように思われます。
このガラスと似たものがカスピ海南に位置するイランの遺跡から見つかっていますが(註1)、それにはポンテ痕が
あり(註2)、円文カットも新沢千塚出土のカットガラス碗より完成度が高いように見え、似たように見えても、両者は
作られた場所が異なるように思えてしまいます。パルティアからササン朝にかけての時代にイランで作られた
カットガラスは正倉院の白瑠璃碗の源流がここに辿り着くのですが、カット技術は非常に高度で、新沢千塚出土
カットガラスのような未完成品とまで言われるようなカットを施したものを見たことがありません。中国でも同類のガラスが
発見されているようです。 新沢千塚出土のガラスについてはまだ分からないことが多いのが現状です。
紺色ガラス皿
口径14.1~14.5cm 高さ3cmの台付き皿。台は別ガラスではなく、1つのガラスで全部が作られています。
台の部分で平らではなく、突出しているため安定性のないお皿。
報告書によれば、この皿の内面にどうやら何か描かれていた痕跡があるようですが、何が描かれていたのかは不明。
復元品にはそこまで再現されておらず、吹きガラスとしての工程を辿ったみたいです。
奇しくも今、台と本体一体型のローマ・ガラスを研究しているため、以前に見たときとは違う見方ができました。
底部が突出してしまった原因もなんとなくイメージしています。これについてはまた実験で試してみたいと思います。
出自に関しては不明。
新沢千塚出土ガラスはそれだけで1つの研究テーマにできるくらい面白いガラスです。
*写真掲載許可済み
註・参考文献
註1 深井晋司 高橋 敏 1973年 『ペルシアのガラス』 p.169
註2 谷一 尚1999年 『ガラスの考古学』 p.139
橿原考古学研究所 1977年 『新沢千塚 126号墳』