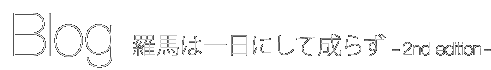アジア文化遺産国際会議に行ってきました2011.03.06
2011年3月3日~5日まで、東京文化財研究所で開催されていました。プログラムはこの研究所のHPを参考に!
さて、このプログラムを見ていただければ分かるように、会議は3日間あり、全部は行けなかったので2日目のレバノン関係の発表がある日を選びました。レバノンより招へいされたアサド・サイーフ氏はレバノン考古局総局のトップで、レバノン入りしたら必ずご挨拶に伺っていました。愛きょうのある方でにこにこ顔が印象的です。数回しか会ってはいませんが、覚えていてくれてたようなないような・・・。ナーデル・シクラウィ氏はティール支局の考古学者で、彼とは遺跡の早朝~夕方まで環境調査をしたり、買い出しに行ったり、とかなり多くの時間をともにし、ネタがたくさんあります。彼らとは宿泊したホテルが一緒で、朝食の時にばったり会い、めっちゃびっくりしてました「なんでここにおるねん?」みたいな。
午前はイラクのお話でした。2003年以降、多国籍軍によりかなりの遺跡が破壊されたこと、また兵士や将校による遺物の占有の話には驚きました。戦争が始まる前に、国内の暴力団により海外へ非常に多くの遺物が持ちだされ、大部分がまだ奪回できていないということです。法整備がされる前に盗掘が行われ、売りに出されるとのこと。そして盗掘するほとんどの人がその価値をしらないで、お金になるということだけで盗掘をするので、丁寧に扱うことがないそうです。
残念ながらヨーロッパの国のなかには文化財の個人所有を認めているところもあり、もし流出品とわかっても取り戻すのが難しいとのこと。このあたりの話は私が読んだ『ユダの福音書を追え』の内容を彷彿とさせます。
驚いたことに戻ってきた遺物は修復されていることがほとんどで、例えばイギリスで修復され、ノルウェーの資産家の手に渡ったものがあったといいます。価値を上げるためなんでしょうか?コレクターがいるとこのような盗掘→オークションという流れができることになります。この日にご縁で一緒に食事をさせていただいたフランス人の先生は「考古学者はコレクションをしてはいけない」とおっしゃっていました。しかし一方で、コレクターによって結果的に遺物が保護・管理されることもあるので、そういったジレンマに悩まされているそうです。
午後はレバノン関係のプレゼンでした。内容としてはレバノンもイスラエルの攻撃により遺跡が被害を受けましたが、問題はどのくらいの規模だったのかが把握できなかったことにあるといいます。そのため遺跡を3Dデジタルデータとして残し、将来、戦争や地震などで被害を受けた時、同じように計測して元データと比較し、被害を確認できるようにするということで、最先端装置を導入、これをレバノン人が自分たちで扱えるように人材育成しているということ。レバノンは今、復興の最中ですが、イラクにくらべまだインフラ整備が比較的進んでいるため、このような一歩すすんだ進行状況となっています。
ほか、ティールの地下墓の保存調査によるプレゼンでは、壁画が色鮮やかにのこっている理由として、室内の温室度の変動差が小さいことがわかってきたこと、年代のわかる様々な遺物が発見されていることなどが発表されました。N大では10年近くレバノンに関わっていることになりますが、ここにきてようやくいろいろなことが見えてくるようになってきたとN教授。研究は本当に地道です。
海外からたくさんの方もいらっしゃっていましたし、日本の研究者もこられていたのでもっとお話をしたかったのですが、残念ながら大阪に戻らねばならずゆっくり話すことができませんでしたが、各分野で活躍されている方のプレゼンを聞くとモチベーションが上がります。がんばらんとあきません。
終電で東京より帰路に着きました。危なかった・・・・
久々に先生方や友人に会えてよかったです。しなければいけないこともいろいろ増えました。