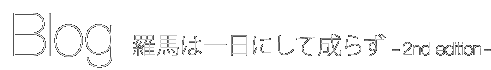第11回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの煌めき」④-12018.02.03
田村朋美 「化学組成と製作技法からみるガラス小玉の産地と交易ルート」
膨大な量のガラス玉を成分分析して、成分や技法別に分け、産地や交易ルートを考察する内容でした。
成分分析によるグルーピングなどはグラフが多用されるため、内容についていくのがやっとでした(笑)。
頭を整理するため、発表内容に補足しながら書き留めます(発表内容と補足の区別はつけてませんが、個人的な追記は註として解説を入れるようにはしています)。
ガラスについて
弥生時代~古墳時代にかけて60万点以上のガラス品が流通していたと考えられている。ほとんどは舶載品で、考古化学的調査をすることで、これらの産地や交易ルートを解き明かそうという研究が行われている。
ガラスの主原料はケイ素、アルカリ分、カルシウム。ケイ素は地球上に無限に存在する「砂(石英)」*1で、これだけを熔かしてもガラス化するが、あまりにも高温(二酸化ケイ素の融点は1710℃)が必要なため、古代の窯では実現することができなかったと思われる。ここにアルカリ分を加えると熔解温度は下がり、古代の窯でも熔かすことができた。
アルカリ分にはいくつかの種類があり、大きく分けてナトリウム、カリウムがある。ナトリウムは植物灰やナトロン(炭酸ソーダ)が原料。カリウムはカリ硝石、ブナの木など森林植物の灰(主に中世ヨーロッパ)が原料。
ナトリウムは水に溶けやすい性質があるため、カルシウムを添加して水に溶けにくいガラスをつくる。これは意図的にしたとも、原料にもともと入っていたともいわれる(例えば海岸の砂をガラス原料に用いたときは、意図せず貝殻由来のカルシウムも添加されることになる)。
ケイ素やカルシウムからは産地推定が難しいが、アルカリ分にナトロンを使ったか、植物灰を使ったかによって、ローマ・ガラスかササン・ガラスかの区別がつく。
第11回アジア考古学四学会合同講演会「アジアの煌めき」②-1参考。
ガラスの成分分析によって地域性があることが分かっている。
- 西アジア・・・ソーダ・ガラス、植物灰ガラス
- 地中海・・・前8世紀:ナトロンガラス→植物灰ガラスへと変わっていく
- 中国・・・前5世紀からガラスが見られる。鉛ガラス、鉛バリウムガラス
- 東南アジア・インド・・・カリガラス、ソーダガラス(高アルミニウム)
続く
註
*1 砂(石英):古代において良質のガラスをつくるには砂の採掘地がある程度決められていた。1世紀の博物学者プリニウスの『博物誌』にはイタリアのヴォルトゥルヌス河口でガラスを作るのに適した砂が発見されたという記述がある(原書第36巻66章、中野他訳1986 p. 1493)。また、2世紀の地理学者ストラボン『地理誌』にはイスラエルのアクレとティールの間の砂浜でガラスの原料砂が採れると書かれている(原書第16巻第2章、飯尾訳 1994 p.494)。少し古い文献だが、古代エジプトのガラス研究においては、砕いた石英を原料に使っていたという考えに対して、この場合だと意図的にカルシウムを添加しなければならないため、石英をガラス原料に使っていたのではなく、自然にカルシウムも含まれている砂漠の砂が使われていたという指摘もある(丸山 1973 p. 45-47)。